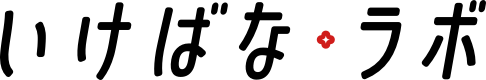いけばなの基本構造
いけばなには数多くの流派があり、それぞれに独自の型や表現方法があります。今回の記事では、その中でも池坊の「生花(しょうか)」を例に取り上げます。生花における基本構造として知られているのが「真(しん)・副(そえ)・体(たい)」で、これは自然の姿を象徴的に表現する三本の主枝であり、いけばなの骨格をつくる大切な考え方です。
生花(しょうか)とは?
「生花(しょうか)」は江戸時代に広まった池坊の様式で、立花のような壮大さに比べ、より簡潔で洗練された表現が特徴です。限られた花材を用いて自然の姿を映し出し、床の間や日常の空間に調和することを目的としています。その中核となるのが「真・副・体」の三本立ての構造です。
真(しん)
真は、最も長く高く伸びる主枝であり、作品全体を支える「主役」の存在です。天を指し示すようにまっすぐに立てられることが多く、自然界の中でいう「太陽に向かって伸びる大樹」や「生命力の象徴」として表現されます。作品の中心軸となるため、その姿が安定感を与えます。
副(そえ)
副は、真に寄り添うように斜めに伸びる枝で、作品に奥行きと広がりを与える役割を持ちます。人間の存在や自然界の調和を象徴するとされ、真を引き立てる「脇役」としての性格があります。副があることで、作品は単なる一本立ちではなく、空間全体に自然な動きを生み出すことができます。
体(たい)
体は、低く横に広がる枝で、作品の安定と基盤を担います。大地や水面を象徴し、真と副を支える存在です。体がしっかりと配置されることで、作品全体が落ち着き、自然界の「根づき」を感じさせます。
三本がつくる調和
真・副・体の三本は、それぞれ「天・人・地」を象徴するといわれます。真=天、副=人、体=地。この三つが調和することで、一つの作品が自然の縮図として完成するのです。花や枝の長さ、角度、配置はこの三本を基準に決められ、そこに他の花材を添えて作品を仕上げていきます。
初心者へのアドバイス
真・副・体という考え方は、一見難しく感じられるかもしれません。しかし、要点は「長い・中くらい・短い」の三本をバランスよく配置することです。たとえばチューリップ三本でも、一本をまっすぐ長く、もう一本を斜めに、最後の一本を低めに配置すれば、自然と「生花らしさ」が表現できます。
「真・副・体」は、池坊の生花における基本的な構造であり、いけばなの世界を理解する上で欠かせない考え方です。他の流派では必ずしも用いられない概念ですが、この三本立ての思想を知ることで、いけばなの根底にある「自然と調和する美」の感覚を学ぶことができます。