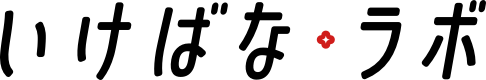お花の3Dモデル制作
Blenderを使って制作
まずは何でも自分でやってみます。3dデータの開発にはBlenderというソフトが良さげということだけ知っていました。オンラインでBlenderの講座を一つ購入しやってみました。くまのぬいぐるみを作成してみるというものでした。いきなり躓きました。めちゃくちゃ難しかったです。ひとまず講座通りに進めて作成はできたのですが、これでお花を作成できるようになるには、めちゃくちゃ時間がかかるということがわかりました。
開発をやめるポイントの一つでした。
学生時代に、とある企業にインターンしていた時に学んだことですが、社長とのある会話が心に残っています。「何度も繰り返し自分でこれからもやっていくものは必死に学べ、それ以外はすべて外注しろ」です。私は考えました。例えばこのアプリの開発のあと、また3Dデータを自分で作っていくことがあるのだろうか、3Dモデリングを自分の強みの一つとしていくのか?そうは思えませんでした。
つまり今回のアプリ開発において、3Dのお花制作は外注するべき、という判断に至りました。
3Dモデラーの知り合いなどいるはずもなく、どうしようかと考え、結果、先程学んだ講座で教えている方に連絡してみることにしました。駄目もとで、アプリの概要と相談依頼を送るとなんと返信が返ってきて、最終的にはモデラーをご紹介いただき、今は一緒にこのアプリを開発するパートナーとなっています。
自分のアイデアや考え、アプリのコンセプトをパワポにまとめておいたのが役に立ちました。何度か打合せを重ね、とりあえず最低限動くアプリを見ていただき、必要なお花のモデルのイメージを伝え、受けてみたいと言っていただくことができました。
しかし、また躓くこととなりました。
どんなお花を作ってもらったらいいの?どれくらい作ったらしたらいいの?どんなお花がいけばなでよく使われるの?疑問だらけでした。
開発をやめるポイントの一つでした。
モデリングするお花をリストアップ
モデリングを依頼するにしても、何を作るのかを決めて依頼しなければなりません。当たり前ですよね。その判断は私がしなければなりませんが、私にはできませんでした。そこでいけばなの先生に質問させていただき、その用途だったらこの本がいいんじゃないと、教えていただき、早速その本をオンラインで購入しました。
その本には、様々な花材一つ一つがのっており、そのお花を使った作例集が載っています。その5冊の本をもとに、出てくる花材を調べ上げ出てくる回数をひたすらエクセルにまとめるという作業を行いました。この本の作例にX回登場している、というのをまとめ上げました。そして、およそ250の花材リストが完成しました。これらの花材があれば、ひとまずいけばなを幅広く体験してもらえるだろうとの前提のもとです。
生け花には花器も必要なので、アプリで使う花器もリストアップします。
ここまで実際の開発(コードを書く時間)の割合0.5割、何を作るか考える、その考えをまとめる時間9.5割です。。
もちろんこのリストは、都度アップデートすることとなります。いけばなを習う中でリストにない花材を使ったときにリストに追加したり。。とはいえリストのベースが完成したので、ようやくモデリングの依頼をすることができました。
こうしてひとつひとつ躓きを乗り越えていくこととなります。
3Dモデルの仕様
このリストアップ作業を終えて、モデリングを開始するわけですが、このひとつひとつのモデルも明確な形を依頼するわけではなく、また、このアプリで使うのに適した形で制作いただくということで、綿密な仕様方針の策定も行いました。
具体的には、例えば実際にお花を生けるときにはほぼすべての場面でお花を花鋏で切ります。茎部分を短くしたり、不要な葉っぱをちぎったり、撓める(ためる)、そういった操作をできるだけ行えるように3Dモデルを作成しなければいけません。デジタル化のメリット・デメリットの部分でも書こうと思いますが、この仕様の調整も難しいポイントでした。
他にも、例えばお花の色が違うけれども形は同じ、という色違いのお花は沢山あるかと思います。例えばチューリップでもたくさんの色がありますよね。その色を簡単に変更出来るようにしたり、模様だけが異なっていたり。容量をできる限り抑えつつ、色変更などの拡張性は持たせる、そのためにはモデリングとアプリ側とで詳細な仕様の策定が不可欠でした。
ああでもないこうでもない、といいながらモデリング担当者と仕様方針を決めさせていただきました。とはいえ、花材のひとつひとつも形を指定はできないので、大きな労力をモデリング担当者にはかけてしまっているなと感じています。
実際にはアプリ開発を進めるにあたり、アプリの仕様を変更する必要が出てきたり、操作性改善のため、容量削減のため、何度も何度も「作成を完了」としたものを修正して頂く必要が出てきました。
膨大な作業を費やし何度も作り直すことによって、少しずつ納得いく形に仕上げることができました。結局のところ、アプリの操作感や使用感、モデルの仕様に必要なものなど、コンセプトと同じで作っていく中でどんどん変わるし、どんどん改善させていく方向が見えてくる。その中で落とし所を見つけて、ようやくファーストリリースに漕ぎ着けたのは感慨深いです。
ポリゴン数とリアリティのバランス
技術的に一番悩んだのは「リアリティ」と「軽さ」のバランスです。
花や葉っぱは細かい部分まで作り込めば作り込むほどポリゴン数が増えて、ファイル容量が増える。そして、動作にも影響する。でも省略しすぎるとチープに見える。
モデリング担当者とも何度もやり取りしながら、「ここはテクスチャで表現する」「ここはモデルを削っても雰囲気は残せる」といった線引きを探しました。本当に地味な調整の繰り返しでした。
特に、花器の砂利に関しては、リアルを追求しすぎてしまい、容量が重くなり、オブジェクトの数も増えてしまい、何度も作り直しという作業の結果、最終的には砂利はテクスチャという画像ファイルで表現することで容量を削減するということとしました。
VisionOS・VR時代を見据えて
そんな中で頭の片隅にあったのが、「将来的にはVisionOSやVRで使えるようする」という構想でした。スマホやタブレットで軽く動くことはもちろん大事。でも、次の時代に備えるなら、ある程度のリアリティも残しておきたい。
だからこそ、「削りすぎない」「でも動く範囲に抑える」という調整は絶対に外せなかったんです。そしてこのせめぎ合いは今でも続いています。