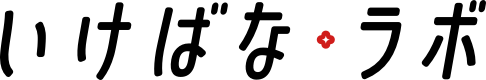いけばな教室に習い始める
ドメインの知識・経験は必須
これまでの経験上、何かしらのサービスやアプリを開発するには、そのドメインの知識・経験は必須です。今回で言えば、私自身がいけばなをやっていなければ、ユーザーに刺さるアプリ・サービスを開発できるわけがない、ということです。なので、大まかなアプリの概要と動くものができた段階で、いけばなを習い始めました。
調べてみると私の住む街には、一人だけ池坊の先生がいらっしゃることがわかりました。すぐに電話をし、簡単な経緯をお伝えし、その先生のもとで学び始めることとなります。それが、だいたい2024年の夏です。
はじめは本当に何もわかりませんでした。右も左もわからない状態の中で、とりあえず、先生に言われるがままというか、こうしてみましょう、という指示通りにいけてみます。それでもイマイチなんかわからない気がします。わからないところはいつも沢山質問させていただいて、少しでも先生の感覚や生き方やいけばなに対する姿勢を学ぼう感じようとしています。2週間に一度の教室では、毎回1時間以上お話をさせていただくことがほとんどです。先生はお話好きなので、ときは全然関係のない話を聞かさせることもあります。。
後に、この初心者での経験が今回のアプリ開発に活きてきます。
そして、このいけばな教室はいまもずっと続けています。本当に楽しいです。
最初のことは、お花の知識もまったくなく、わけがわからないことだらけでした。池坊の生花はいけばなではなく、しょうかと読む、ややこしい!と思ったこともあります。
はじめて生花(しょうか)をやったのは、菊の一種生でしたが、その時は生花の良さをまったく感じることができませんでした。真・副・体というのがある、というのを初めて知りました。
お花の道具も何も持っていなかった私に、先生は花器や花鋏を貸していただき、家でも同じように生けてみなさいとのことでした。とりあえずやってみましたが、なんだかうまくいきません。何度目かでようやく、「お、ちょっとなんかいい感じにいけれたかも」と思ったりもしました。花の扱いもそのころはよくわかっておらず、数日でからしてしまうこともありました。
道端に咲く花
ところで、このようにお花のことを1日中考えていると、ふと今まで見えてこなかったことが見えてくるようになりました。
普段は気にすることのなかった何気ない道端に咲いている花や花壇をみて、これはなんのお花かな、なんていう草なのかな、と思うようになりました。今までは気にもとめたことなかったものが気になるようになってきました。
このようにして、いけばなに触れることで自分の日常が変わっていくことが実感できました。これまで感動することのなかったものに感動するようになり、思わず道端に咲いている花の写真を取るようになったり。しまいには、新たに道端に咲いている草花の図鑑を買って読むようになったり。
この自分自身の変化を私個人は良いことと捉えていて、自分の人生をより豊かにするものだと感じています。このアプリを通じて少しでもそのような感動が伝わっていけばいいなと思っています。
自分の部屋で生けた花が花開いたり、少し倒れてきて心配したり、そうなったらそうなったで、少し短く切っていけなおして、今の状態で一番輝くようにいけなおしてみたり。毎日お水を上げて枯れないように気をつけたり。いつの間に自分ってこんなにお花が好きだったっけ?と笑いました。
以前の自分だったら絶対にスルーしていた景色が、ちょっとした発見の場に変わっていく。これだけでも人生に彩りが増えたような気がしました。
真・副・体
池坊の生花(しょうか)の基本構造は「真・副・体」です。これを習っているときにふと頭に浮かんだのが「黄金比」でした。人が美しいと感じる比率があるように、この三本の枝の関係にも、同じような普遍的な美の法則があるんじゃないか。
もちろん学術的にどうなのかは分かりません。ただ、実際にいけてみて「あ、これだ」と腑に落ちる瞬間があって、そのときの納得感は数字や理屈じゃ説明できないものでした。
初めて、菊の生花一種生を経験したときにはわかりませんでしたが、様々な流派の書籍も読み、いけばなの経験を積んでいくうちに、なんとなく美意識というかセンスが磨かれてきた気がします。
何度も先生が不等辺三角形という言葉を教えてくれているのを、なんとなく感覚的に掴めてきたと感じれたときには嬉しくなりました。
入口や補助としてのアプリの役割
こうして自分で学びながら感じたのは、「やっぱり本物には勝てない」ということ。でも同時に、「だからこそアプリで体験の入口を作る意味がある」とも思いました。
最初の一歩を踏み出すのは誰にとっても難しい。でもスマホで触れてみて、「ちょっとやってみようかな」と思える人が一人でも増えたら、その先に本物の教室や作品との出会いがあるかもしれない。
その入口をこのアプリで作ることができたら、このアプリをリリースする意味はあるんじゃないか、そう強く感じるようになりました。いけばなを実際に習い続ける中で、アプリのコンセプトにも一つ磨きがかかった瞬間でした。
デジタルで体験してもらうことに意味はあるけれど、本当の魅力は実際に花に触れたときにしか分からない。これはアプリの立ち位置を考える上で大きな気づきになりました。