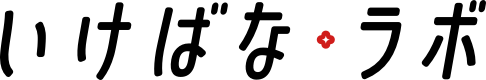お稽古の経験から生まれた新機能
スタイルモード ― 型から学べる入口
最初のバージョンを人に触ってもらったとき、一番多かった感想は「操作が難しい」でした。
自分自身もいけばなを始めた頃に「自由花で、自分の感性でいけてください」と言われて、どうしていいか全く分からなかった経験があります。自由に表現していいと言われても、土台となる基礎や型がなければ逆に動けなくなる。
そうした経験からいけばな未経験者には、「最初の一歩を支える仕組み」が必要だと考え、スタイルモードを開発しました。
これはあらかじめ用意された型に沿って花材をタップしていくだけで、それらしい作品ができあがるモードです。ただ完成するだけでなく、配置の中で自然と「真・副・体」などの構造も学べるようになっています。
初心者にとっては「とりあえず置いてみたら、それっぽくできた」という成功体験が大事です。そこから少しずつ基本を知っていき、慣れてきたら自由な表現へ進める。スタイルモードは、まさにその入口を担っています。
現時点ではまだ用意できているスタイルの数は多くありません。ですが、少しずつ充実させていくつもりですし、経験者や先生方の知見をお借りしながら、より実践的で学びのあるスタイルを増やしていけたらと思っています。
もちろん、自由に挑戦したい人にはノーマルモードがあります。こちらは制約なくいけられる分、難しさも伴います。だからこそ、スタイルモードとノーマルモードを並べることで、「型から学び、自由へ挑む」という流れを自然に体験できるようにしました。これは完全に、自分が初心者のときに「最初にもう少し型を学べたら良かった」と思った経験から生まれた発想です。
とはいえ、まだまだスタイルモードとノーマルモードの間には、簡単さと自由度という点で、大きな乖離がありスタイルモードを経験したからといって、すぐにノーマルモードで自由に創作が出来るとは言えないので、まだまだ改善の余地ありと捉えています。
デジタル花展 ― 見てもらえる場所、広がる展示会
もうひとつの大きな機能がデジタル花展です。 これは、実際のいけばな作品をアプリ上で公開し、他の人に見てもらえる仕組みです。コメントや「いいね」を通じて、世界中の華道家やユーザーと交流することもできます。
発想のきっかけは、これも実際にお稽古に通っていたことでした。毎回の作品をInstagramにアップしていたのですが、誰かに見てもらえるだけでも嬉しく、先生や他の人から反応をもらえるとさらに嬉しい。その体験が「人に見てもらえる場の大切さ」を強く意識するきっかけになりました。
さらに、先生から「そろそろ花展を見に行ってみたら」と勧められて実際に足を運んだことも大きな経験でした。会場に並ぶ作品を見て、「同じ花材でもこんなに表現が変わるのか」と驚き、作品を通して伝わる力に圧倒されました。展示され、誰かに見てもらえることが、作り手にとってどれだけ大きな意味を持つのかを実感しました。
ただ、実際の展覧会は誰でも気軽に参加できるわけではありません。準備や会場、時間の制約があり、ハードルは高いものです。そこで「もしアプリの中に常設の展覧会があったら」と考えました。
デジタルであれば、場所や時間に縛られずに世界中の人が参加できます。初心者も経験者も、自分の作品を気軽に発表でき、他の人の作品を見て回れる。まさに「常設のデジタル花展」です。
アプリをきっかけにいけばなを始めた人も、長く続けている人も、同じ場所に集い互いの作品を見合える。そんな「見てもらえる喜び」を大切にしたいと思っています。
参考写真 ― 花材から学べる
さらに追加したのが参考写真機能です。 花材一覧から任意の花材を選ぶと、その花材を使った作品をまとめて見ることができます。3Dの作品もあれば、写真として投稿された実際のいけばなの2Dの作品の写真もある。ひとつの花材がどう使われているかを一覧できるので、実際のお稽古で花材に向き合うときにも大きな参考になりえます。
「この花材をどう生かせばいいのか」「他の人はどんなふうに使っているのか」。その答えをすぐに探せることが、自分の表現の幅を広げるきっかけになります。初心者にとっては迷わない安心感になり、経験者にとっても新しい発想のヒントになります。
続けるための仕組み
振り返ると、スタイルモードも、デジタル花展も、参考写真も――どれも自分が実際にいけばなを習い、体験してきた中で感じたことから生まれました。
「自由すぎて最初はどうしていいか分からなかった」 「作品を見てもらえるのが嬉しかった」 「見本があると安心できた」
その一つひとつの実感が、機能の形になったものです。だからこそ、同じように感じる人の役に立てるのではないかと思っています。
「いけばなラボ」をただの作成ツールで終わらせるのではなく、「学べる」「共有できる」「参考になる」場所にしていく。そんな思いで少しずつ継続的に開発を続けていきます。