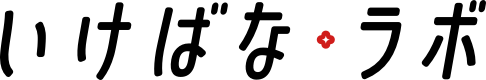ビジネスと未来展望
サブスクと広告モデルの考え方
アプリを作る以上、どうやって収益を得るかは避けられない課題です。最初の頃は「無料で公開してもいいんじゃないか」と思っていましたが、開発や運用を続けるにはどうしてもお金が必要になります。ここは現実的に考えざるを得ませんでした。
サブスクで「花材や花器のバリエーションを増やせるようにする」案や、広告を入れて「無料でも遊べるけど少し制限がある」仕組みなど、いろいろ試行錯誤しています。まだ正解が見えているわけではありませんが、一つだけ大事にしているのは「収益化のために世界観を壊さない」ということ。いけばなという文化を扱う以上、ビジネスの仕組みよりも文化への敬意を優先することを常に心に置いています。
1000年の伝統とデジタルの融合
いけばなは1000年以上続いてきた日本の伝統文化です。その世界をスマホの中に持ち込むことに、最初は「そんなことをしていいのか?」という迷いもありました。デジタル化することで軽く見られてしまうのではないか、と。
でも続けてみて分かったのは、「本物を壊すことではなく、入口を広げることができる」ということでした。アプリをきっかけにいけばなに触れる人が一人でも増えるなら、それはいけばな全体の裾野を広げることにつながると信じています。
世界中の華道家へ ― ARからVRへ
今はiPhoneやiPadでの体験が中心ですが、将来的にはARで部屋に作品を設置して楽しむだけではなく、VisionOSやVRで立体的にいけばな制作できるようにしたいと考えています。最初に「これを3Dで体験できたら面白い」と思った原点に、少しずつ近づいているように感じます。
もちろん技術の進歩には時間がかかります。AppleやMeta、SONYなどが次々と新しい製品を出していますが、まだ誰もが日常的に使うには遠い存在です。ただ、医療や教育などの分野ではすでに活用が始まっていて、いずれ生活にもっと自然に溶け込む時代が来るはずです。
その未来を考えると、このアプリの可能性にもワクワクします。
3Dデータの価値
今の時代、AIはコードを書いたり、文章を生成したり、多くのことができるようになっています。ただ「何かを作りたい」と思う欲求まではAIにはありません。だからこそ、私自身が考え、言葉や形にして残していくことに意味があると思っています。
「いけばなラボ」で使う花や器の3Dデータは、すべて人の手でモデリングしています。AIではまだ難しい作業であり、モデルごとに仕様を調整しているのも、優秀なモデラーと出会えたからこそ実現できていることです。だからこそ、一つひとつのデータには大きな価値があると感じています。
そして、このデータの価値は今後さらに高まっていくはずです。ARやVRの発展において必要不可欠なのは、ベースとなるのは3Dデータだからです。このアプリのために制作した花材や器といった3Dデータは、今後新しい技術の橋渡しになると信じています。
正直に言えば、このアプリはまだ社会的には少し「早すぎる」のかもしれません。私自身も日常的にARやVRの世界で暮らしているわけではもちろんありません。でも、いずれその分野が発展した先には、ここで積み上げてきたデータや仕組みがきっと役立つ。たとえアプリが思うように広まらなくても、この挑戦自体が無駄になることはないと考えています。